投信定期売却サービスと分配型投信の違い~保有口数が減るか否か
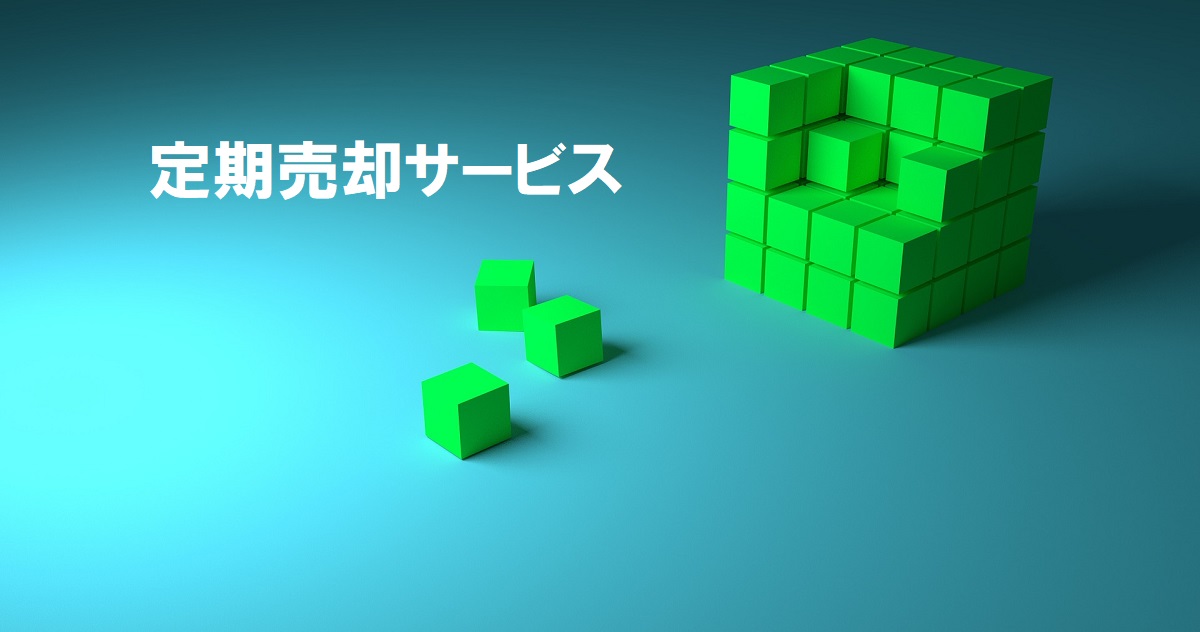
投資信託の「定期売却サービス」をご存知でしょうか?
SBI証券では2012年からサービスを提供していますが、楽天証券を始めとする他の証券会社も2019年末からサービスの提供を始めました。
分配型投信の分配金の受け取りと似た感覚で利用できて便利ですが、両者の違いは何でしょうか?
投信の定期売却サービスの概要~「定額・定数・定率」の3方式
投資信託の定期売却サービスは、保有している投信を定期的に自動で売却するサービスです。
サービスを提供している証券会社には、SBI証券、楽天証券、セゾン証券、フィデリティ証券などがあります(2020年8月時点)。
各社がサービスの提供を始めた時期は次のとおりで、最も古いSBI証券は2012年から始めていますが、他の証券会社も2019年末からサービスを提供するようになりました。
- SBI証券:2012年3月16日(投資信託定期売却サービス開始のお知らせ)
- 楽天証券:2019年12月29日(投信定期売却サービス開始)
- セゾン証券:2020年春(予定)(定期売却サービス提供のお知らせ)
- フィデリティ証券:2020年8月2日(投信自動定期売却、自動定期出金)
売却方法には「①定額、②定数、③定率(金額または口数)」があり、各社で異なります(下表)。また、売却の頻度については、毎月や隔月のほかに、SBI証券ではボーナス月(年2回まで)を指定できます。
| 売却方式 | 内容 | 住信SBI | 楽天 | セゾン | フィデリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| 定額売却 | 一定の金額を定期的に売却 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定数売却 | 一定の口数を定期的に売却 | - | ○ | ○ | - |
| 定率売却(金額) | 一定率の金額を定期的に売却 | - | - | - | ○ |
| 定率売却(口数) | 一定率の口数を定期的に売却 | - | ○ | - | - |
売却方式によって、保有口数の減り方に差が出る
保有する投資信託を部分的に売却するので、どの方式であっても「保有口数が減る」ことに変わりはありませんが、保有口数の減り方は売却方式によって異なります。
例えば、10万口を保有している場合、1万口の「定数売却」ならば、売却のたびに保有口数が1万口ずつ減り、10回売却すると保有口数がゼロになります。
10%の「定率売却(口数)」ならば、初回は1万口を売却しますが、2回目は0.9万口(9万口×10%)の売却になり、回を追うごとに売却口数が減ります。
「定額売却」や「定率売却(金額)」では、売却口数はその時の基準価額によって増減します。
売却方式による売却口数の違いを整理すると次のようになります。
| 売却方式 | 内容 | 売却口数の変化 |
|---|---|---|
| 定額売却 | 一定の金額を定期的に売却 | その時の基準価額によって増減 |
| 定数売却 | 一定の口数を定期的に売却 | 毎回同じ |
| 定率売却(金額) | 一定率の金額を定期的に売却 | その時の基準価額によって増減 |
| 定率売却(口数) | 一定率の口数を定期的に売却 | 回を追うごとに減少 |
分配型投信の分配金との違い~保有口数が減るか否か
例えば、定期売却サービスを「定額売却」で利用すると、定期的に一定の金額を受け取れるので、分配型投信の分配金と似たような感覚になります。
では、定期売却サービスの定額売却と、分配型投信の分配金の受け取りでは何が違うのでしょうか?
違いは保有口数が減るか否かです。定期売却サービスでは保有口数が減りますが、分配型投信の分配金を受け取っても保有口数は減りません。その代わり、払い出した分配金のぶん基準価額が下がります。
どちらも「運用しながら資産を取り崩す」というニーズに応えていますが、保有口数が減るか、基準価額が下がるかにおいて違いがあります(下表)。
| 資産の取り崩し方法 | 保有口数は減る? | 基準価額は下がる? |
|---|---|---|
| 定期売却サービスの定額売却 | 減る | 下がらない |
| 分配型投信の分配金の受取 | 減らない | 分配金のぶん下がる |
「運用しながら資産を取り崩す」という目的を理解していれば、どちらを利用してもよいでしょう。しいて言うと、保有口数が確実に減っていく定期売却サービスの方が「資産の取り崩しに力点を置いている」といえそうです。
まとめ
投資信託の定期売却サービスについて紹介しました。
- SBI証券は2012年からサービスを提供しているが、2019年末から楽天証券、セゾン証券、フィデリティ証券などでもサービスを提供し始めた
- 定期売却の方式には、定額、定数、定率(金額、口数)があり、証券会社によって利用できる方式が異なる
- 売却の頻度は、毎月や隔月が主流だが、ボーナス月を指定できる証券会社もある
- 分配型投信の分配金と似ているが、両者の違いは保有口数が減るか否か。定期売却サービスでは保有口数が減る。分配金の受け取りでは保有口数は減らないが、基準価額が下がる
- 定期売却サービスも分配型投信の分配金の受け取りも「運用しながら資産を取り崩す」というニーズに応えているが、定期売却サービスは資産の取り崩しに力点を置いている

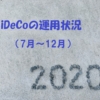





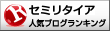

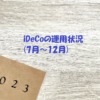
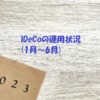







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません