暴落時にできることは限られる~晴れているうちに屋根を修理

今回のコロナショックで再認識したこと。それは、資産運用において暴落時にできることは「ほとんど何もない」ということです。やるべきことは全て暴落前にあります。
コロナショックにおける運用資産の下落率は30%弱今回のコロナショッ ...
資産クラス別のリターンの推移から分かること

前の記事「リスク・リターン分析を利用して優秀なファンドを選好する」で紹介したように、リスクやリターンの値は資産クラスによって異なります。一般に、リスクの大きい資産クラスほど得られるリターンも大きいわけで、リスク・リターン分析のグラフを ...
リスク・リターン分析を利用して優秀なファンドを選好する
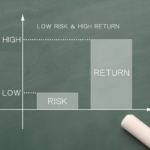
ファンドを選ぶ際には、どうしてもリターンの大きなファンドに目を奪われがちですが、そのリターンを得るためにどのくらいのリスクを取る必要があるか?を把握しておくことが大切です。そのためにリスク・リターン分析を活用しましょう。
リスク ...分配金が引き下げられたときに確認すべきこと

毎月分配型の投資信託を何本か保有していると、分配金の引き下げに遭遇することがあります。何だか残念な気持ちになるものですが、ファンドの運用資産を保全するための措置ですから仕方のないことです。
保有しているファンドの分配金が引 ...
ファンドの最大下落率を確認しておく

保有ファンドが「過去に最大でどのくらい下落したか?」を知っておくことは、リセッション(景気後退)や “〇〇ショック” と呼ばれるような突然のマーケット・クラッシュに対する備えとして大切です。IMFの発表した最新 ...
資産の取り崩しシミュレーション

私は長期で運用する資産を少しずつ取り崩しながら早期退職後の生活費の一部に充てています。このとき、取り崩す金額を上手にコントロールしないと、資産がすぐに底を尽きてしまいます。
取り崩し額と資産寿命との関係は、資産の運用効率や ...
アセット・アロケーションは7:2:1

我が家では、資産を長期で運用しながらその一部を少しずつ引き出して退職後の生活費に充てています。その際に、分配型投資信託やSBI証券の投資信託定期売却サービスなどを利用しています。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)についても、SBI ...
投資信託の慎重な選び方~押さえるべき7つの情報と分配金の健全性

私は長期で運用する資産の一部を少しずつ取り崩しながら、退職後の生活費に充てています。その手段として、分配型投資信託やSBI証券の「投資信託定期売却サービス」を利用しています。
分配型投資信託を利用して、運用しながら資産を「取り崩 ...分配型投資信託を利用して、運用しながら資産を「取り崩す」

我が家の家計収入においては、今のところ「長期資産運用による収入(取り崩しながら運用)」が比較的大きな割合を占めています。また、その際に利用している商品は「分配型投資信託」です。
資産を「取り崩す」というと、マイナスのイメー ...