暴落時にできることは限られる~晴れているうちに屋根を修理

今回のコロナショックで再認識したこと。それは、資産運用において暴落時にできることは「ほとんど何もない」ということです。やるべきことは全て暴落前にあります。
コロナショックにおける運用資産の下落率は30%弱
今回のコロナショックでは、私の運用資産の評価額は一時的に大きく下がりました。
iDeCoの資産(インデックスファンドで運用)の評価額は一時的に約25%の下落。また、生活費充当用の資産(アクティブファンドで運用)の評価額は一時的に約28%の下落を記録しました。
※2019年12月末の資産残高を基準
生活費充当用の資産の評価額が底を打ったのは3月24日です。この時の管理ファイル(Excel)は、三陸沿岸の津波碑(津波がここまで来たことを後世に残すための碑)のように永久保存するつもりです。
私は「株式:債券:金=7:2:1」というアセット・アロケーションで分散投資しているのでこの程度の下落で済みましたが、資産クラスによっては次表に示すようにもっと大きな下落率になります。
※詳しくは「コロナショックにおける資産クラス別の下落率」にまとめています。
| 資産クラス | 代表的な指数 | 下落率 |
|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX | ▼28.2% |
| 先進国株式 | MSCIコクサイ(除く日本) | ▼32.2% |
| 新興国株式 | 新興国株式指数(MSIS) | ▼33.3% |
| 国内REIT | 東証REIT | ▼46.6% |
| 先進国REIT | FTSE EPRA/NAREIT 先進国不動産(除く米国) | ▼39.6% |
4月に入ってから比較的早いスピードで回復しつつありますが、まだ下落前の水準には戻っていません。
暴落時に気づく低パフォーマンス・ファンドの存在
今回のような暴落とその後の回復を経験すると、自分の保有ファンドに関して(残念ながら…)ある事に気づくことがあります。それは、「パフォーマンスの悪いアクティブファンドの存在」です。
具体的には、次のようなパフォーマンスのファンドです。
- 暴落時には、評価額の下げがカテゴリ平均よりも大きい
- 回復時には、評価額の戻りが悪い
このようなファンドを「低パフォーマンス・ファンド」と呼ぶことにしましょう。次に挙げるような特徴のファンドであることが多いですが、パフォーマンスの悪さは平常時には気づきにくく、暴落とその後の回復期を経て初めて気づくので厄介です。
- リスク・リターン分析においてリターンがカテゴリ平均よりも劣る
- リスク・リターン分析においてリスクがカテゴリ平均よりも大きい
- 5年以上運用されているのに、設定来のトータルリターンがマイナス
- 5年以上保有しているのに、トータルリターンがマイナス
- 分配金利回りが高くなっている(目安として、10%以上)
- 分配金の減額が頻繁におこる
- 通貨選択型である
- 運用にオプション取引を組み込んでいる
- 信託報酬手数料がカテゴリ平均よりも高い
該当する項目が多いファンドを保有している場合は、そのパフォーマンスを注視しておきましょう。
私の場合、iDeCoはインデックスファンドで運用しているので問題ありませんが、生活費充当用の資産はアクティブファンドで運用しており、かつて低パフォーマンス・ファンドを保有していました。
暴落時には何もできない
では、このようなファンドを運悪く(いや、不勉強のために)保有していることに気づいたとき、それをいつ処分(他のファンドに資金を移動)すれば良いかですが、それは暴落時ではありません。
指数の暴落が始まり、資産の評価額が大きく減り始めると経験上もう何もできません。指数の下落の大きさに唖然とし、評価額の目減りにうんざりし、「一体いつ底をつけるのだろう…?」と眺めるだけの我慢の日々が続きます。
今回のコロナショックでは、1月から2月にかけて徐々に雲行きが怪しくなり、3月に一気に暴落しました。私の運用資産の評価額は3月24日に底を付けましたが、それも今だから分かることであって、落ちている最中には「今が底」ということも分かりません。
暴落の始まりに気づいたとき、低パフォーマンス・ファンドを保有していると、とても後悔します。「何で処分しておかなかったのだろう…」と。そのファンドについては、評価額がこれから大きく下がり、回復時には戻りが悪いことが想像できるからです。
しかし今回は、この後悔をせずに済みました。相場状況が良いときに低パフォーマンス・ファンドをコツコツと処分していたからです。
そのような備えができたのは、以前の暴落時に後悔し、「屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る」という教えの大切さを痛感したからでした。
晴れているうちに屋根を修理する
これは、ジョン・F・ケネディ(アメリカ合衆国第35代大統領)の教えです。原文とその訳は次のとおり。
The time to repair the roof is when the sun is shining.
屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る。
ジョン・F・ケネディ(第35代米国大統領、1917~1963)
「雨が降り始めてから屋根を修理しても遅い」ということを言っています。その通りです。屋根に穴があるならば、雨が降る前にふさいでおく。つまり、「潜在的な問題があるならば、顕在化する前に処置せよ」という教えです。
前述したように、暴落時には何もできません。低パフォーマンス・ファンドの処分などのメンテナンスは、相場状況が良いとき(日が照っているうち)だからできるのです。
コロナショックの前、世界経済はとても良い状況でした。その間、具体的には2019年秋から年末にかけて、気になっていた低パフォーマンス・ファンドをコツコツと処分しました。
今回のコロナ相場においては、「やれることはやった」という思いがあったので、不安になりながらも腹をくくって状況を見ていました。
なお、昨年処分したファンドのうちの幾つかはトータルリターンがマイナスです。含み損のファンドを売却するのはとても苦痛ですが、ここでは「失われたものを数えるな。残っているものを最大限に生かせ」という教えに従いました。
残ったものを最大限に生かす
これは、「パラリンピックの父」と言われているルートヴィヒ・グットマン(Ludwig Guttman, 1899~1980)の教えです。この言葉の出所は必ずしも明確ではないそうですが、英語、日本語では一般に次のように表現されています。
It is ability, not disability that counts.
失われたものを数えるな。残っているものを最大限に生かせ
ルートヴィヒ・グットマン(Ludwig Guttman, 1899~1980)
これはとても実践ハードルの高い教えです。なぜなら、「失われた」ことを受け入れるのは誰にとっても苦痛だからです。
含み損のファンドを売却するときも同様。例えば、100万円で購入したファンドの評価額が80万円に目減りしたとします。評価損はマイナス20万円。
長期投資の観点からは先々の回復を見込んでこのファンドを保有し続けるべきですが、もし回復が見込めないファンドだとしたら…。苦痛ですが、評価額がさらに下がる前に売却し、資金を他のファンドで運用する方がよいと思います。
このとき、20万円の損失(失われたもの)を数えると売れなくなりますが、80万円の資産残高(残っているもの)を生かすことに目を向ければ売却できます。
まとめ
今回のコロナショックによる運用資産の目減りとその後の回復を振り返って、改めて大切さを痛感した心得を2つ紹介しました。
「屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る」。相場状況が良好なときに低パフォーマンス・ファンドのような不良資産を処分しておく。なぜなら、暴落が始まると経験上何もできないから。
処分する際の心得は、「失われたものを数えるな。残っているものを最大限に生かせ」。含み損には目を向けず、残資産を生かすことに目を向ける。
経済環境はまだ回復の途上ですが、穏やかな晴れの日が戻ってきたら、次なる暴落に備えて屋根を修理しておこうと思います。
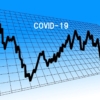




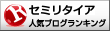

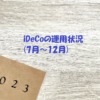
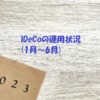







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません