投信分配金が少し増えるかも~「二重課税調整制度」とは

2020年1月から、一部の投資信託の分配金が微妙に増えていることにお気づきでしょうか? 理由は「投資信託等の二重課税調整制度」という税制改正が1月1日に施行されたからです。
この制度は、投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国と国内で二重に課税しないように調整するというものです。嬉しいですね。裏返せば、これまでは二重に課税されていたということですね。
制度の概要と、分配金がどの程度増えるのかを計算例と共に紹介します。
税制改正の概要
日本証券業協会のサイトの「証券投資の税制」に、「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」というお知らせ(PDF)がありますので、ここから今回の税制改正の概要を引用します。
これまで、お客様が証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
引用元:日本証券業協会『投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内』 ※マーカーは管理人が引きました
これについて、証券業界は改善を要望していたところ、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりましたので、制度の概要についてご案内いたします。
要は、外国株式等への投資から生じた利益が分配金に含まれている場合、「これまでは、外国と国内で二重に課税されていたが、二重に課税しないための調整を2020年1月から行う」というものです。
次のとおり、調整の対象となるのは「外国株式等に投資する投資信託やETF・JREIT・JDR」です。ただし、NISA口座で保有しているものについては、そもそも国内は非課税なので調整の対象外です。
二重課税調整措置の対象となるのは、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等です。これらの投資信託等が2020年1月1日以降に支払う分配金については、自動的に二重課税調整が行われます。ただし、対象となる投資信託等をNISA口座で保有されている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しませんので、本措置の対象となりません。
引用元:日本証券業協会『投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内』 ※マーカーは管理人が引きました
お客様が保有されている投資信託等のうち、本措置の対象となる上場商品(ETF・JREIT・JDR)については、今後、東京証券取引所ホームページにてご確認いただけるようになる予定です。
また、 調整結果は年間取引報告書や支払通知書で確認できる旨もお知らせに記載されています。では、二重課税調整の具体的な計算方法を次に紹介しましょう。
二重課税調整の計算方法
まずは、分配金に対する税金の計算方法をおさらいします。分配金には普通分配金と特別分配金があり、このうち普通分配金に対して所得税(15.315%)と住民税(5%)を計算し、それらを引いた残りが受取分配金になります。
- 分配金(普通分配金、特別分配金)を計算
普通分配金=口数×普通分配金単価
特別分配金=口数×特別分配金単価 - 所得税を計算
所得税=普通分配金×15.315% - 住民税を計算
住民税=普通分配金×5% - 受取分配金を計算
受取分配金=普通分配金+特別分配金-所得税-住民税
これが、今回の税制改正によって次のように変わります。黄色マーカー部分が変化点です。
- 分配金(普通分配金、特別分配金)を計算
普通分配金=口数×普通分配金単価+「加算対象額」
特別分配金=口数×特別分配金単価 - 所得税を計算
所得税=普通分配金×15.315%-「控除額」 - 住民税を計算
住民税=普通分配金×5% - 受取分配金を計算
受取分配金=普通分配金+特別分配金-所得税-住民税
変更内容を整理すると、次の2点になります。
- 普通分配金に「加算対象額」を加えてから所得税を計算する
外国において徴収された納税額(外国所得税額)を「加算対象額」として普通分配金に加算します。
- 計算された所得税から「控除額」を差し引く
二重課税にならないように、一定の外国所得税額を「控除額」として控除します。「控除額」≦「加算対象額」という関係があります。
- より詳しい説明に関しては、日本証券業協会の「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」を参照してください。
抽象的で分かりにくいので、具体的な計算例を次に示しましょう。
二重課税調整の計算例
私の保有ファンドの2020年1月、2月の支払通知書を例に、実際の計算方法を紹介します。分かりやすいように、次の3例を紹介しましょう。
- 普通分配金のみの投信A(控除額=加算対象額)の例
- 普通分配金のみの投信B(控除額<加算対象額)の例
- 特別分配金が発生した投信Cの例
「加算対象額」と「控除額」は支払通知書に記載されていますが、証券会社によっては「控除額」だけが記載されていることがあり、その場合は「控除額」=「加算対象額」とみなします。なお、小数点以下の端数処理は証券会社によって異なる可能性があるので、ご注意ください。
普通分配金のみの投信A(控除額=加算対象額)の例
投信Aの支払通知書の概要は次のとおりでした。特別分配金は発生していません。また、「加算対象額」の記載はないので、「控除額」と同額の7円とみなします。
- 数量:2,335,981口
- 分配金単価:10円(1万口あたり)
- 全て普通分配金
- 控除額(外国税相当額等):7円
受取分配金は次のように計算されます。
- 分配金の計算
普通分配金=10円×(2,335,981口÷10,000)=2,336円 ※小数点以下四捨五入
特別分配金=0円 - 普通分配金に「加算対象額」を加算
2,336円+7円=2,343円 - 所得税の計算(「控除額」を減算)
2,343円×15.315%-7円=351円 ※小数点以下切り捨て - 住民税の計算
2,343円×5%=117円 ※小数点以下切り捨て - 受取分配金の計算
2,336円+0円-351円-117円=1,868円
受取分配金が幾ら増えたかを計算するには、「控除額」を0円にした場合との差を計算すればよいですね。実際に計算すると、5円になります。少額ですが、嬉しいものです。
普通分配金のみの投信B(控除額<加算対象額)の例
投信Bの支払通知書の概要は次のとおりでした。特別分配金は発生していません。また、「加算対象額」と「控除額」が異なる金額で記載されています。
- 数量:4,000,000口
- 分配金単価:15円(1万口あたり)
- 全て普通分配金
- 加算対象額:3,356円
- 控除額:1,324円
受取分配金は次のように計算されます。
- 分配金の計算
普通分配金=15円×(4,000,000口÷10,000)=6,000円
特別分配金=0円 - 普通分配金に「加算対象額」を加算
6,000円+3,356円=9,356円 - 所得税の計算(「控除額」を減算)
9,356円×15.315%-1,324円=108円 ※小数点以下切り捨て - 住民税の計算
9,356円×5%=467円 ※小数点以下切り捨て - 受取分配金の計算
6,000円+0円-108円-467円=5,425円
受取分配金が幾ら増えたかを計算するために、「加算対象額」と「控除額」を0円にした場合との差を計算すると、643円になります。これは大きな金額ですね。
特別分配金が発生した投信Cの例
投信Cの支払通知書の概要は次のとおりで、特別分配金が発生しています。また、「加算対象額」と「控除額」は同額で記載されています。
- 数量:4,000,000口
- 分配金単価:25円(1万口あたり)
- 普通分配金2円+特別分配金23円
- 加算対象額:24円
- 控除額:24円
受取分配金は次のように計算されます。
- 分配金の計算
普通分配金=2円×(4,000,000口÷10,000)=800円
特別分配金=23円×(4,000,000口÷10,000)=9,200円 - 普通分配金に「加算対象額」を加算
800円+24円=824円 - 所得税の計算(「控除額」を減算)
824円×15.315%-24円=102円 ※小数点以下切り捨て - 住民税の計算
824円×5%=41円 ※小数点以下切り捨て - 受取分配金の計算
800円+9,200円-102円-41円=9,857円
受取分配金が幾ら増えたかを計算するために、「加算対象額」と「控除額」を0円にした場合との差を計算すると、19円でした。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 2020年1月から始まった「二重課税調整制度」について紹介しました。ポイントをまとめると、次のようになります。
- 投信分配金に外国株式等への投資から生じた利益が含まれている場合、これまでは、外国と国内で二重に課税されていたが、二重に課税しないための調整が1月から始まった
- NISAで保有するファンドについては、そもそも国内は非課税なので調整の対象外
- 同じ理由で、特別分配金についても調整の対象外
- 二重課税調整の計算におけるポイントは、次の2点
- 普通分配金に「加算対象額」を足してから所得税を計算(「加算対象額」で外国所得税額を考慮)
- 得られた所得税から「控除額」を減算(二重課税にならないように、一定の外国所得税額を控除)
- 「加算対象額」と「控除額」は、支払通知書等で確認できる
これまでのところ、受取分配金の増え方はファンドによって数円~数百円という幅がある状況です。しばらくは、自分でも検算してみようと思います。
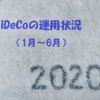





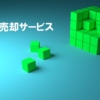
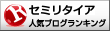

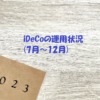
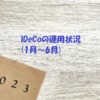







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません